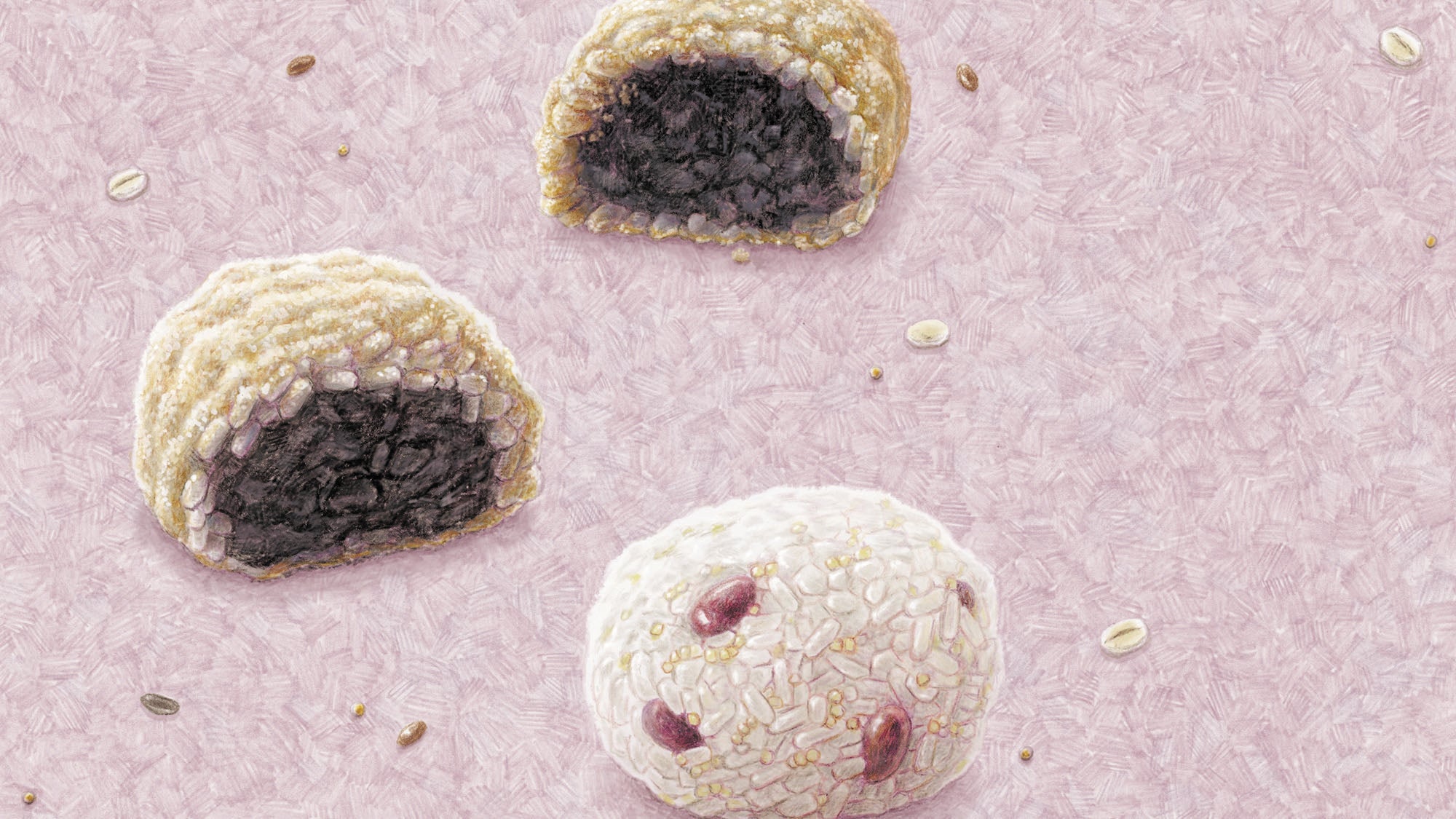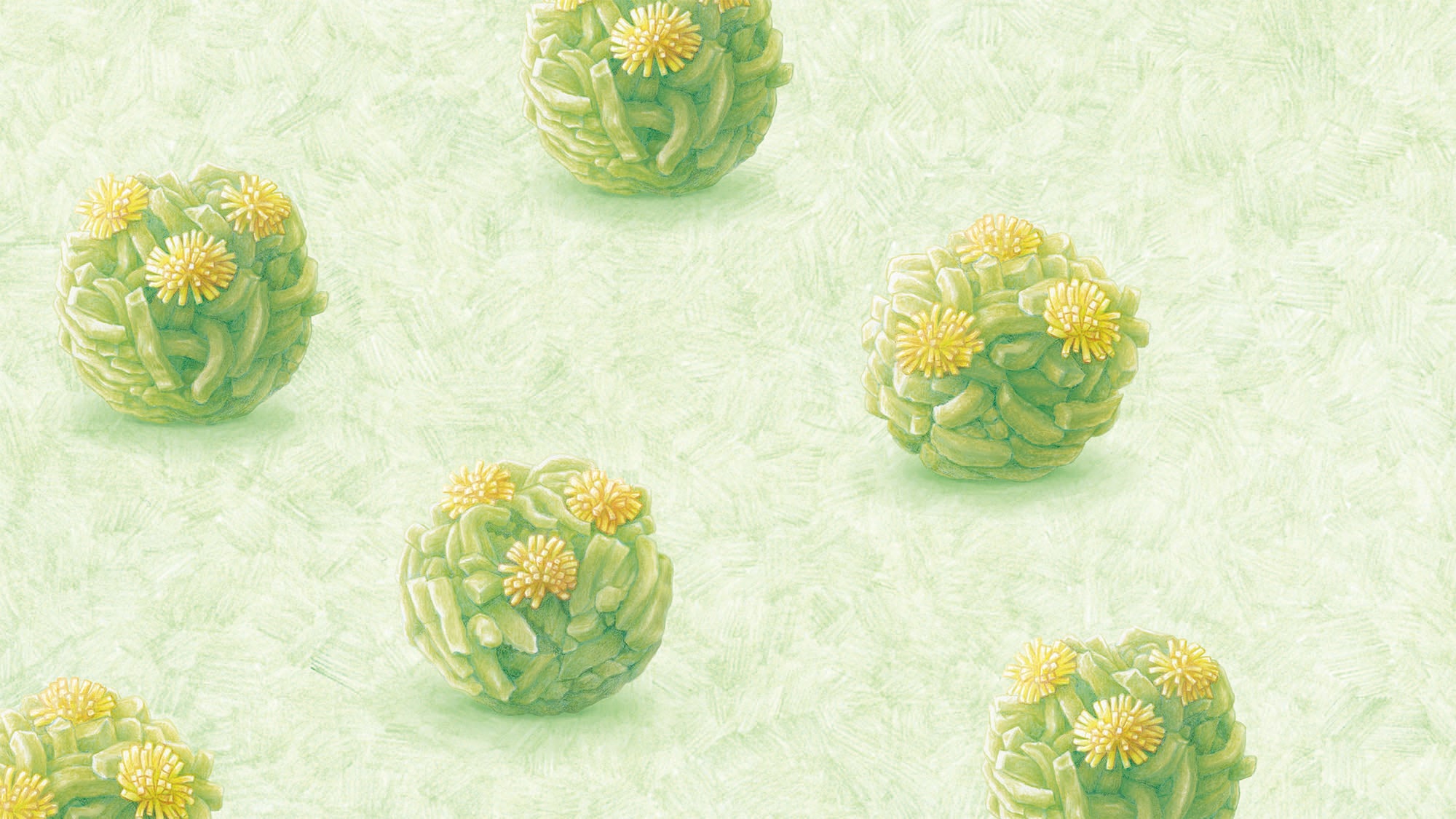- 読みもの
- お買いもの
- TTJ
- 東京茶寮
- 私達について
-
作家名一覧
- 煎茶堂東京
- 四十沢木材工芸
- 阿部春弥
- 天野千香
- 荒賀文成
- 安齋新・厚子
- 飯高幸作
- 石田誠
- 伊藤萠子
- 稲村真耶
- 入江佑子
- 色原昌希
- Eliu
- 遠藤岳
- 淡海陶芸研究所
- 大江憲一
- 大澤知美
- おじろ角物店
- 小野陽介
- 角田清兵衛商店
- 樫原ヒロ
- 加藤かずみ
- 紙上征江
- 亀田大介
- 亀田文
- 北井里佳
- 紀平佳丈
- 黒川登紀子
- 光泉窯
- 児玉修治
- 後藤睦
- 後藤義国
- 小林裕之・希
- 小宮崇
- 齋藤有希子
- 作山窯
- 酒匂ふみ
- SHISEI
- 清水なお子
- シャンブリートリオ
- 秀野真希
- 松徳硝子
- 白鷺木工
- 須原健夫
- 瀬戸國勝
- 千田稚子
- 相馬佳織
- 高木剛
- 高橋禎彦
- 竹下努
- 多田佳豫
- 只木芳明
- TATA pottery studio(田中大輝)
- タナカシゲオ
- 田中大輝
- ちいさな手仕事
- 蝶野秀紀
- 塚本友太
- 土井善男
- とりもと硝子店
- 中里花子
- 中原真希
- 中村譲司
- 中村豊実
- 萩原千春
- 畠山雄介
- はなクラフト
- 濱岡健太郎
- 林沙也加
- 広末裕子
- フじイまさよ
- 藤村佳澄
- 船串篤司
- 古谷宣幸
- 文山窯
- 堀宏治
- 三浦ナオコ
- 水野悠祐
- 光藤佐
- 南裕基
- 三野直子
- 三輪周太郎
- mrak
- 村上雄一
- 村田匠也
- 森岡希世子
- 山田哲也
- YŌKI
- 横山拓也
- 李荘窯
- WASHIZUKA GLASS STUDIO
- 渡辺キエ

機械に”揉まされてる”んじゃなくて僕は機械で揉んでるんで 「022 かなやみどり」柚木善彦さんインタビュー
2020年07月19日
by 煎茶堂東京編集部
≫ 映像コンテンツでお茶を選ぶ(一覧)
童仙房は、京都南部にある山の頂上に位置する京都唯一の村です。山の山頂が開けた盆地のようになっており、標高が450〜500mほど。平地との気温差は5℃ほどもあり、夏でも涼しく、12月中旬から雪が降ります。
水道が通っていないので、水源は井戸水を利用していて、山頂だというのにところどころから湧き水が滲み出しているという美しき秘境の情感がそこにはあります。村までの深い山道は、大雨などが降ると土砂や倒木で道が断絶したりするので平易な道のりではありません。
そんな秘境の地で格別のお茶を作る柚木さんに、お話をお聞きしました。
話し手:柚木善彦さん 聞き手:谷本幹人
―――柚木さんのお茶は形状も綺麗だし、特別香りが良い。今日はその秘密を聞かせていただきたいのですが、まずはこちらの工場のご説明をいただいていいですか?
見ての通り工場はもうよその最新鋭に比べると全然古い。木造の合掌組なんですよ。僕が中学校3年生ぐらいのときからなんで、もう35年ぐらいは経ってます。
うちの先代にあたる父親のときに後継者が要るっていうことで、工場を新設しておこうって建てたんです。当時鉄骨がみんな主流だったんですけどうちの親父は木造にこだわる派だったんで、木造の工場で白壁造りにした方がいいんちゃう、と。今となったら珍しい。

―――なかなかこんな綺麗な白壁の工場なんてみないですね。
工場の設計がこれ60キロの機械ラインで、当時の主流やったんです。そのとき僕が後継者にでたんで将来的に90キロをハーフライン入れようかなと、もうひとサイズ大きい機械を入れるつもりで工場を設計してもらったんで、若干天井が高くなってるんですよ。
それがいまうまく回ってきて工場自体も気温が涼し目になるっていう効果が得られてる。たまたまなんですけどね。結局90キロラインをいれようかなっていうよりも60キロラインの機械の台数を増やした方が品質がいいものができるんちゃうかということで、結局60キロラインをずっと使う方針に変わったんですよ。
―――機械を変えずにそのまま。他には何か変えていったところは?
粗揉機を2台にしたんですよ。普通1台で1時間やるやつを、2台にして半分ずついれたら進んでいく速度が倍になるんで。1台でやると1時間いっぱいかかるところを2台にして、あと精揉機をもう1台増やしたらトントントンとリズムよく30分サイクルぐらいで流れて処理能力が上がるんですよ。
なおかつ機械のセッティングとして1台でずっと回すより、2台でバネ圧とか攪拌(かくはん)の揉み手の設定を変えたほうがいい。お茶の容積は、はじめは生葉の状態のやつが入ってるんですけど、揉まれてくると徐々にかさが低くなってくるんで。もし同じ設定でやってたら葉ざらいにかかってくる量が減って、揉みこまれる力がだんだん弱まってくるんですよ。
だから、かさが減ってきたぐらいの変わり目に注意して、若干セッティングを変えた2台の構造にしておくと、またそこでかさの容積に合わしたセッティングで揉み込むことができるんです。
―――生葉の栽培から荒茶の製造まで、個人でやられてるからこそのお話ですよね。地域によっては共同工場の方がやるとか分業されてるじゃないですか。
京都は元々個人工場が多いんでそういうところが多いんですよね。経営してはるその人の個性がでるじゃないですか。市場にでたときに、宇治の方の茶師さんたちは特徴だすのに面白みをもってされる方が多いじゃないですか。個人工場の個性を大事にされてるんで、この辺のみんながうまく回ってたんでしょうね。
逆にドリンクメーカーさんやったら共同工場の大きなロットのをドンドンってまとめた方が商品が安定するので、それはそういう方向に行きはるんでしょうけど。
こじんまりと小さい営業をうまく回していくような感じでやると、個性のある商品をだしやすい。自分で自分なりのセッティングができるんで。
―――個性を出すための機械のセッティングに。
いまやと、この葉ざらいと底竹(ていちく)の隙間とか揉み手のバネ圧ですよね。そういった物の作用でお茶の水分の蒸散値がすごい変わるんです。

粗揉機の説明をしてくださる柚木さん。底竹と葉ざらいの隙間と、揉み手のバネ圧を調整する。
―――機械セッティングで大切なバネ圧の調整は感覚なんですか?
いや、ちゃんと測ります。専用の機械で張力を測ります。中を擦りながら茶葉が上がってくるんで、その擦り合わせる圧力で水分を出す量を調整するんです。その出た分を温風で飛ばしてあげて、効率良く乾かしていく…って本にはそう書かれてあるんで(笑)。
それを追求していくんです。蒸したすぐの葉は水分も多いですし、かさも高いんでその分水が出てくるのが早いんです。それに伴う蒸発が葉の温度を減らそうとします。粗揉機の中では、揉み手がバネ圧をかけて揉み、その後ろで葉ざらいがかきあげていく。この葉ざらいがかき上げて、高いところから落とすんです。お茶がふわっと浮く。落ちていく瞬間に乾くわけなんで、その秒を底竹との隙間で調整するわけです。
―――葉ざらいと底までの隙間…ですか。
底竹との間の距離があるんです。これが狭いとお茶の葉がかき上がりすぎて揉まれずにぐるぐる回ってる状態。これが広いとお茶の葉が滑ってしまって下で回ってしまう状態。その中間のいい所をしっかりと捉えているかを判断するためにこのクリアな扉があるわけです。
―――なるほど。機械の中を覗きながら調整するんですね。
お茶が揉まれずに回るだけだと、ただ風にあたって乾いちゃうんで、葉の中の水分が抜けずに赤みのさした茶ができてくるんです。だから、自分でカスタマイズをやって追求するんです。最後伸びる葉を造るために。
キリキリっと最後まで絞り出すためにはそんだけの粘りと柔らかさがないとなかなかできない。粗揉の揉み込みが一番メインです、やっぱり。
―――粗揉の揉み込みが柚木さんのお茶の秘訣なんですね!先程のお話だと、ここから2台目の粗揉機へ流れていくわけですね。
はい、かさが変わると機械の必要な容積が変わる。容積が変わってくると風が当たる量が変わってくるんで、色合いが変わってくるっていう。色の冴えが出てくるとか出ないとかいうのがあるんです。


―――柚木さんのつくりたい理想のお茶はどんなお茶ですか?
理想としては、葉の形状的には今のがほぼ完成できてきてると思います。あとは味のコクみたいな、まろみみたいな、喉ごしがなめらかなお茶がつくりたいです。
そのためにはやっぱり揉まないと駄目だと。茶の全体の中から、茶の旨味成分を絞り出すようにしっかり揉んで葉を柔らかくして、中から全てを取り出しきるみたいなお茶をつくらないと駄目なんです。僕も昔は味が硬いお茶やったんですよ。揉んで柔らかくして、でも形はしっかりとあるっていうお茶をつくらないと駄目だっていうのが分かったんです。
やっぱり1本1本きれいに針のように、砕けずにもまれてあると、急須の中で開いて、蒸した状態の茶葉に戻るじゃないですか。その復元力の高いお茶をつくらないと。お茶は乾物なんで砕いちゃうともうその復元力はなくなっちゃうんで、いかに残すかってなってくると優しくきれいに丁寧にもんでいかないと。1枚ずつ開いていくお茶をつくりたいじゃないですか。

―――柚木さんのやられている「芽重型(がじゅうがた)」の茶園作りというのはどういうものでしょうか?
茶園の剪定をするときに芽がいっぱいでるように剪定するか、芽が少なくなるように選定するか。
芽が少ないほうがその分栄養がしっかりのるという芽重型。芽数型のように芽が多いと性質が変わってきて香りがよい方向性になったりします。
芽の数と重さをどうするかっていう、分け方の一つになってるんです。芽重型の方が旨味がのる。芽数型の方が香気としてはよくのるっていわれるんですけど。
―――芽重型は茶園の面積に対して贅沢な作りですね。
芽数は減るんですけどその分芽が重たく作れます。あと軸(茎)がたくさんあるんで、軸からでてくるうまみがたくさんのる。芽数型にすると軸が細いんで見た目はきれいです。
芽重型でやっていくと葉が大きくなる分、蒸の時間を長くしてあげないとならないんです。軸が太いんで蒸さりきらないっていう。
童仙房は標高が高いんで、蒸気の温度が低いんですよ。だからボイラーの中の管圧を上げるんです。管圧を上げるとプラス5℃ぐらいまで最大上げることができるんで。そうすると蒸気温度は若干上がってくる。
―――なるほど、そこは童仙房で芽重型をされる柚木さんならではの工夫ですね。高さと気温と。
そういうことも本に書かれてるんですよ(笑)
お茶の話を「TOKYO TEA JOURNAL」 でもっと知る
このインタビューは、「観て飲む」お茶の定期便 "TOKYO TEA JOURNAL"に掲載されたものです。毎月お茶にまつわるお話と、2種類の茶葉をセットでお届け中。
関連記事
-
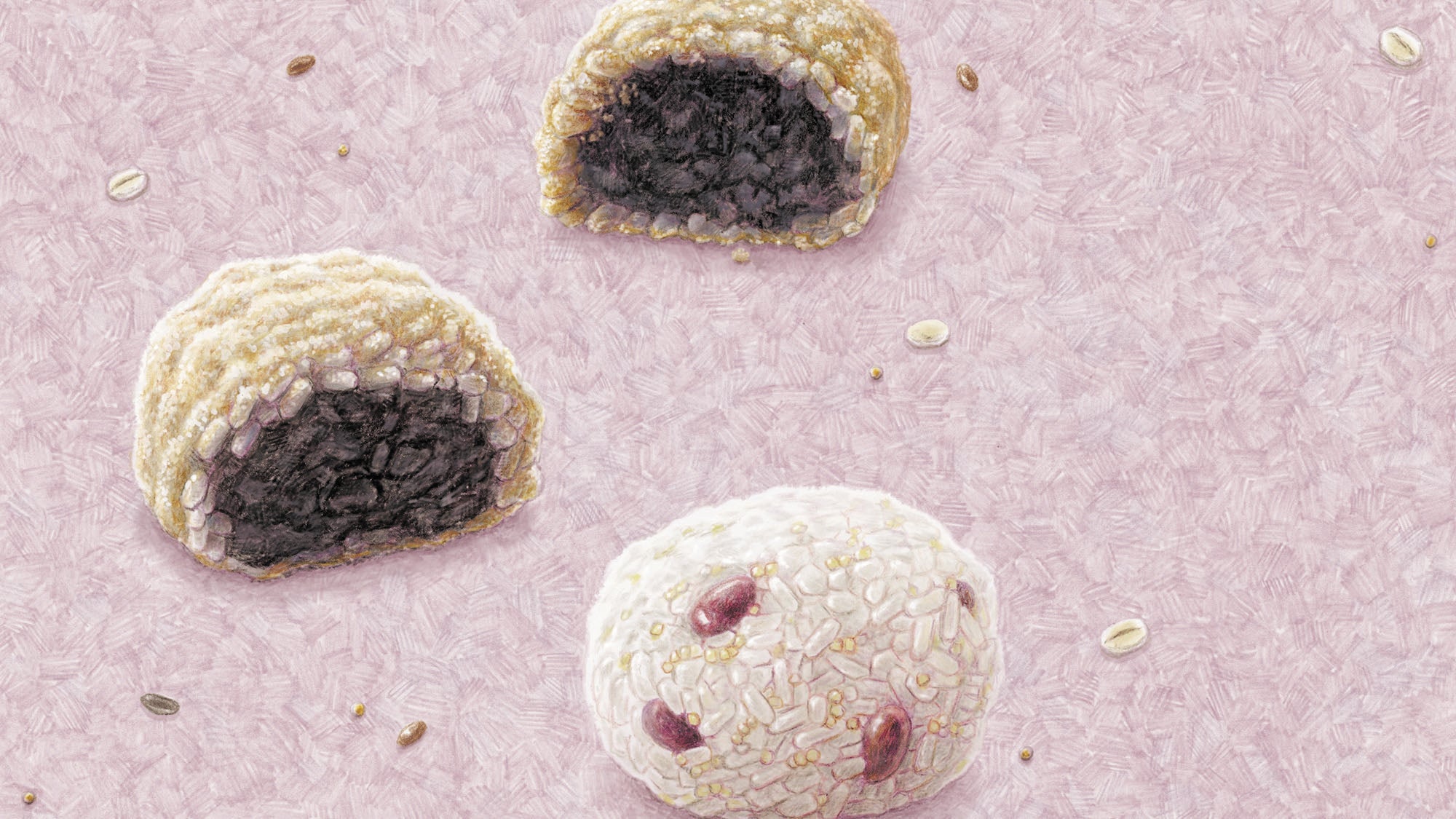
【11月号】TTJ VOL.79
2025年10月01日
-

【10月号】TTJ VOL.78
2025年09月01日
-
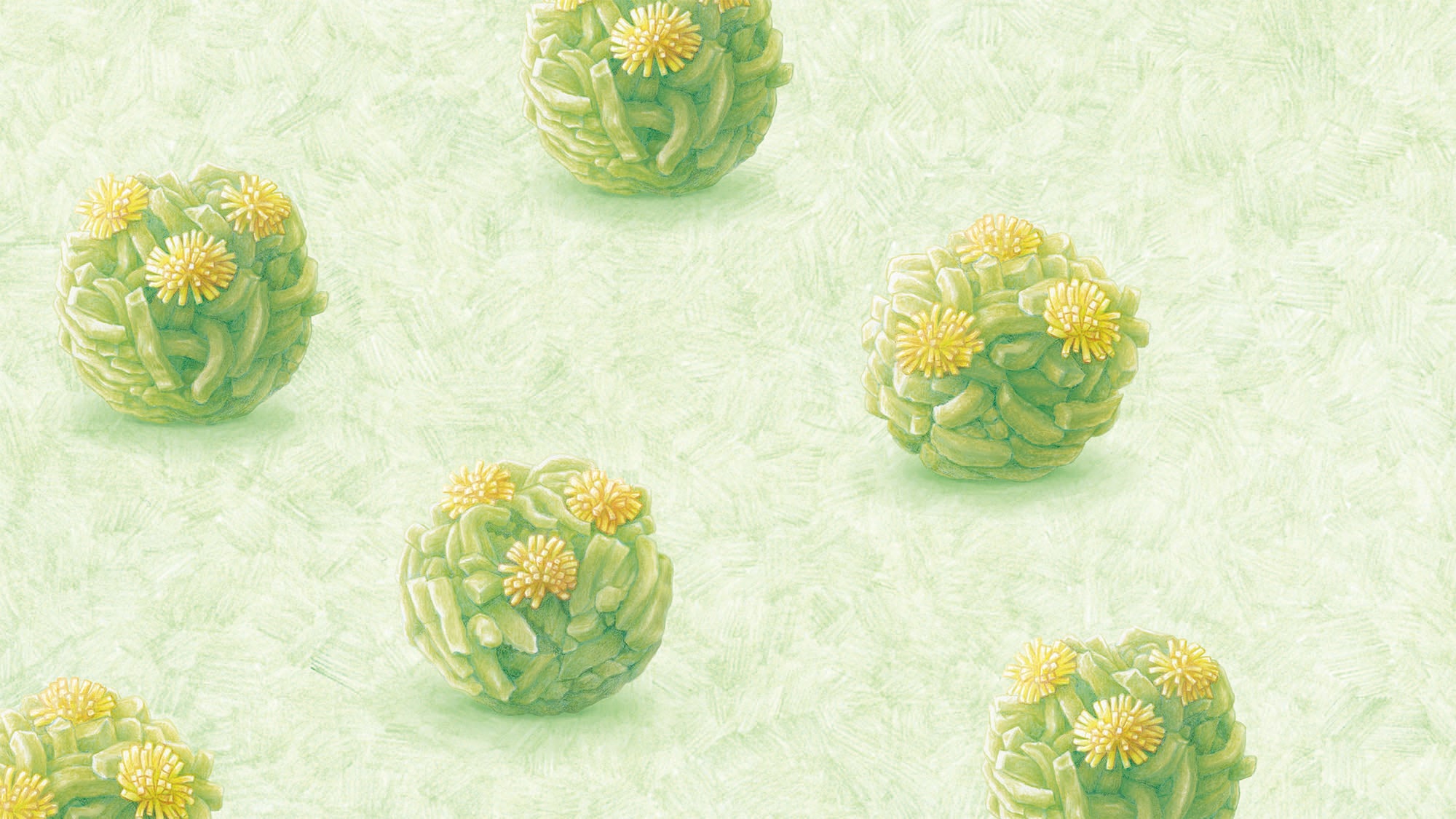
【3月号】TTJ VOL.59
2024年02月01日
-

【試飲茶会】2023年9月販売のシングルオリジン煎茶2種を飲み比べてみました!
2023年09月01日
-

【試飲茶会】2022年9月販売のシングルオリジン煎茶2種を飲み比べてみました!
2022年09月01日
-

【お菓子とお茶】大人の乙女心をくすぐる松本・開運堂「白鳥の湖」と「ジャスミンティー」で上品な儚いティータイム
2021年10月04日
-

【お菓子とお茶】わたしの小確幸な時間。ギフトにもぴったりなNUMBER SUGAR「クラシックキャラメル」と「022 かなやみどり」
2020年11月11日
-

椎茸とお茶のうま味相乗効果で味わう秋の味覚。「肉なし肉じゃが」と「022かなやみどり」レシピ
2020年10月09日
傷もまったくわからなかった。
どこが二級品?となるくらいの綺麗なものが届いて大満足。傷があっても美味しいお茶を淹れられればいいとは思っていましたが、浮いたお金で和紅茶を一緒に買わせていただきました。
とても温かみのある色合い、手触り、見た目の質感です◯お客様へのお茶とお菓子の受け皿として、朝のフルーツを盛る器として、1人用のサラダ皿として、色々なシーンで使わせていただきます❁ご紹介くださりありがとうございました。
楕円皿はいくつか持っていて購入を迷いましたが 買ってよかったです。大きさ・フチの立ち上がりの感じもいい感じです。また 粉引の質感も土も魅力たっぷりです。
初めて手揉みの緑茶をいただきました。
一煎目から煎を重ねるごとに変わってゆく風味と味わいの深さ、そして色合いの美しいこと!
また、飲み終えてからの茶葉を食べてみた時の美味しさに驚きました!!
早速、手揉み茶の魅力にハマってしまいました。他のお茶も味わうのが楽しみです。
造形の美しさに惹かれます。茶碗の膨らみや受け皿のへりにかけての曲面が、シャープでありながら優しいです。器の表面が滑らかな石膏のような素朴な手触りで、オフホワイトの色調と合って暖かみを感じます。
台湾茶を飲む時間が、日常生活の句読点となり、リフレッシュできました。
重量感がある見た目に反して非常に軽く使いやすいです。いつものティータイムを引き締めてくれる深みがあります。これから使い込んでいって違った顔を見せてくれるのかと思うと楽しみです
思いがけず長く抽出してしまいましたが、渋みやエグ味等はなく、ただただ烏龍茶の華やかな香りが広がります。マスクしていても香ってくるくらいです。
味はコクがある中でも、癖がなく、さわやかなのでとても飲みやすいと思います。
烏龍茶の香りが好き!という方は是非飲んでみてもらいたいお茶です。
お正月に元旦用にと。ところが、着たら飲みたくなり試飲。
まろやかな味わい、もうひとつ購入悩み中、売れきれる前に
私は楕円のプレートが大好きです!
深さ有るものからとてもフラットな大小色々な種類を持ってますが、いざ購入して使ってみると、今ひとつしっくり来ない感覚でいました。。。
「児玉修治オーバルプレート」の画像を見た時に「これだ!」と思い、入荷待ちの末ようやく届きました♡
ベストサイズ・ふっくらした楕円・ニュアンスのあるホワイト・個性的マットな質感・リムの絶妙な大きさと立ち上がり寸法、ずっと求めてた全てを満たしてくれました。このプレートに盛ると、シンプルな料理がアートっぽく感じて毎日楽しんでいます!
ケーキやフルーツも素敵に見せてくれます。
封を開けた瞬間の香りの良さ、1煎目の旨みと優しい口当たり、そして2煎目のより味わい深い旨みが緑茶を楽しむという事に対する満足感を与えてくれる一品となっております
届いて手に取ってみると予想していたお品より更に素敵で大変満足しています。色も形も手触りも素材もとても好ましく ただそこにのっているだけで湯のみでもお菓子でも一輪挿しでも倍魅力的に見える気がします。大切に使わせていただきます。
この冊子を読むと、煎茶の味わい深さや、個性が分かるので、煎茶堂東京銀座店でお茶を買った暁には、読み返したりしています。
デザインや文字のフォント。見やすくて好きです。
また、3種類のお茶を飲む時も、是非、冊子を開いて、読みながらやって頂くと、より楽しめます。
丸っこいかたちに一目惚れして「お抹茶を立てて飲みにくいかな?」と思っていましたが、その心配は全くなく最後のひと口まで美味しく吸い切れます。お抹茶茶碗はいくつか持っていますが、お気に入りの1つになりました。

 ログイン
ログイン カート
カート