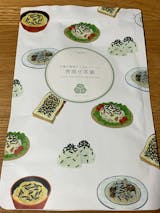禅とお茶の密な関係〜茶道が持つ深い精神性とは〜
2021年06月08日
お茶の歴史は禅と密接に関わっていると言うと、あまりピンとこない人が多いかもしれません。日本では茶の湯や茶道(抹茶道)を通してお茶文化が広まっていきましたが、茶道と臨済宗・曹洞宗・黄檗宗(おうばくしゅう)といった禅宗は切っても切り離せない関係なのです。
今回は、日本へ本格的なお茶文化をもたらした臨済宗の僧・栄西(えいさい・ようさい)の時代より脈々と続く、日本における禅とお茶の関係性についてご紹介していきます。
上流階級の嗜みだった日本におけるお茶
そもそも、日本でいつ頃からお茶が飲まれるようになったかについては諸説あります。奈良時代の正倉院文書(しょうそういんもんじょ)などにそれらしき記載が見られるものの、確実な文献として残っているわけではありません。
正式な文書として残っている最古の記録は、平安時代初期に編纂された『日本後紀』におけるものと言われています。本書の中で、京の僧・永忠(えいちゅう)が当時の嵯峨天皇にお茶を煎じ奉ったという記録があるのです。
実際、平安時代には朝廷の中に茶園が設置され、季御読経(きのみどきょう)と呼ばれる宮中の重要行事において、当時貴重だったお茶が丁重に振る舞われていました。ただ、この時代のお茶文化は上流階級に限られていたと考えられ、広くお茶が普及していくのは鎌倉時代になってからのことでした。
臨済宗の僧 栄西がもたらした抹茶の風習

宮廷の中で細々と受け継がれていた日本のお茶文化でしたが、鎌倉時代になると少し様子が変わります。1191年に宋での修行から帰国した栄西が、当時宋の禅宗寺院で流行していた抹茶を日本へもたらしたのです。
栄西は禅宗の臨済宗を日本に伝えた僧であり、抹茶は禅宗寺院を中心に広がりを見せることになります。座禅を中心とした厳しい修行を特徴とする禅宗では、悟りを開く上であらゆる欲望や煩悩を無くすことが大切。中でも、睡眠欲を忘れることは最も難しいことです。
だからこそ睡眠欲を消し去ることが、煩悩から解き放たれ悟りに近づく重要なポイントとなります。禅宗寺院では修行中の睡眠欲を晴らし、厳しい修行に再び集中するための手段として、カフェインを多く含む抹茶を服することが重視されました。つまり、お茶は覚醒効果をもたらす「薬」だったのです。
鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』において、栄西が二日酔いに苦しむ三代将軍・実朝(さねとも)に茶を勧めたという記録が残っていること、栄西自身が茶の効能についてまとめた『喫茶養生記』を記していることからも、お茶が薬として認知されていた様子がうかがい知れます。
まとめると、栄西が禅宗とともに抹茶をもたらしたことが日本のお茶文化のルーツであり、この時点ですでに禅とお茶は切り離せない関係にあったと言えるでしょう。
臨済宗・曹洞宗 和合の精神を説く茶礼

鎌倉時代には臨済宗の他、道元によって曹洞宗が日本へもたらされ、禅宗が根付いていきました。繰り返しになりますが、禅の修行においてお茶は欠かせないもの。今でも禅寺では茶礼(されい)という儀礼が行われています。
茶礼は朝の座禅の後、食事後、就寝前など一日に数回、一つのやかんから淹れたお茶を修行僧みんなで分けて飲むという作法。仲間同士で同じお茶を飲むという行為を通じて、和合(わごう:異なる2つ以上の性質のものが、お互いに融和して一体となる状態のこと)の精神を説くのです。
このことからも、禅宗とお茶がいかに密接な関わりを持ってきたかおわかりいただけるのではないでしょうか。
禅の思想を取り込んだわび茶の誕生
世は武士の時代。日々鍛錬に明け暮れる武士たちにとって、修行によって自らの心を鍛える禅は受け入れやすいものだったと考えられます。武士の存在感が高まるにつれて禅宗も広がりを見せ、一体的だったお茶文化も武士の間に浸透していきました。この点でも、お茶と禅はセットだったのですね。
時代は下って南北朝時代になると、闘茶(とうちゃ)と呼ばれる一種の賭け事が武士や庶民の間で流行します。飲んだお茶の銘柄を当てるというもので、あまりの流行ぶりに禁止令が出るほどでした。
加えて、大名たちの中には大金を叩いて本場中国の茶器を集め、豪華絢爛な茶会を開く者まで現れます。そんな娯楽要素の強まったお茶の世界に対し異を唱えたのが、茶道の祖と言われる村田珠光(むらたじゅこう・しゅこう)でした。
珠光は、かの有名な臨済宗の僧・一休宗純に参禅したとされる人物。お茶に禅の思想を加えることで、わび茶(茶の湯の一種)を生み出したのです。具体的には、四畳半の質素な和室において少人数でお茶を喫することにより、精神的なつながりを持つことを目的としました。
かつて禅とセットでもたらされたお茶は、禅の思想を取り込むことで、深い精神性を獲得していくことになるのです。
茶の湯から茶道へ
戦国時代になり、千利休によって茶の湯は大成されます。織田信長・豊臣秀吉という時の天下人に仕えた利休の存在は、茶の湯の社会的地位を存分に高めました。利休が秀吉との対立によって壮絶な最期を迎えたのは有名ですが、利休が描いていた茶の湯の理想が対立の一因であったと考えられています。
その理想を強く表しているのが「家は洩らぬほど、食事は飢えぬほどにて足ることなり」という言葉。家は雨漏りしない程度、食べ物は飢えない程度あればいいという意味で、必要以上の欲を捨て質素に生きる大切さを説いています。
禅が目指すのは、全ての欲望や煩悩を消し去り、悟りの境地に至ることであるというお話をしました。利休が思い描いた茶の湯の理想は、まさに禅の思想を反映したものと言えるのです。
利休の思想は、北野大茶湯(きたののおおちゃのゆ)と呼ばれる大茶会を催したり、豪華絢爛な黄金の茶室を作ったり、何かと派手好きだった秀吉とは対照的。両者の思想の違いが対立のきっかけになったことは想像に難くありません。
大名たちが好んで嗜んだことにより、権力と結びついて形骸化してしまった茶の湯でしたが、江戸時代半ば以降精神性を重んじる本来の姿が再び見直されるようになります。ここでも臨済宗の禅寺が大きな役割を果たしたとされ、より禅の思想を強く反映した茶道が確立されていったのです。
明治期に活躍した思想家・岡倉天心は、代表作『The book of tea(茶の本)』の中で茶の湯・茶道のことを英語で「teaism」と表現しています。通常「tea ceremony」と訳されるのですが、天心は茶道が単なる儀式ではなく精神的な意味の強い宗教的なものと捉えていました。
日本のお茶文化は禅の思想に基づく深い精神性を持つことにより、独自の文化として根付くことができたと言えるのかもしれません。
黄檗宗の僧 売茶翁の精神を受け継ぐ煎茶道

戦国時代にかけて形式化してしまった抹茶道に対し、江戸時代になると煎茶道が確立されます。形式を目的とせず、禅の思想をルーツとする精神世界やつながりを重んじる煎茶道は、形式化を嫌う文人たちに広く受け入れられました。
煎茶道の根底には、江戸時代に始まった禅宗である黄檗宗(おうばくしゅう)の僧・高遊外(こうゆうがい)の存在があります。高遊外は売茶翁(ばいさおう)とも呼ばれ、京の市中でお茶を売り歩くことで庶民にお茶文化を広めた人物です。
身分や貧富の差に関係なく、誰でもお茶を通じて禅の思想に触れることができるという点において、煎茶道は元来の「茶道」の理想を強く感じさせるものとなっています。
お茶を通じて自分自身や相手と心を通わす大切さ
文中でもご紹介した岡倉天心は「the book of tea」の中で、茶道について次のように述べています。
茶の理想の頂点は日本の茶の湯にこそ見出される。(中略)私たち日本人にとって茶道は単に茶の飲み方の極意というだけのものではない。それは、生きる術を授ける宗教なのである。
(岡倉天心著、大久保喬樹訳(2005)『ビギナーズ 日本の思想 新訳 茶の本』角川ソフィア文庫 P50)
茶道(抹茶道)においては精神統一が求められますが、普段のティータイムはもちろん肩肘張る必要はありません。一人でお茶を淹れてホッと一息つく瞬間、家族や友人と語らいながらお茶を共にする瞬間、お茶を通して自分や他人と向き合っていること自体が禅の思想に結びついているのです。
新型コロナ感染拡大の影響で人と会う機会が減っている現在、たまにはお茶を共に飲みながら、和合の時間に身を委ねてみるのもいいかもしれません。
久しぶりに大好物のドライいちじくをいただきました。いちじく本来のほんのり甘い品のいいお味が凝縮されていて、噛めば噛むほど口のなかに甘みが広がります。程よい柔らかさと粒々食感も最高です。今回は「はるもえぎ」と共にいただきました。
昨年、賞味期限前の値引きの時に購入しました。美味しかったので再購入。少しお高いですが非常に美味しく、緑茶と合わせると最高です。ケーキより糖分が少なく、タンパク質が取れるのも良いと思います。
私は毎朝、起床時に緑茶を飲むのが習慣になっています。当初は緑茶が飲めればそれでよかったのですが、見た目や雰囲気も含めてお茶の時間を楽しみたいと考えるようになり、素敵だなと思える茶器を探していました。そんな中、この急須を見つけました。
約180mlのお湯が入る容量があり、1人でコップ1杯分飲むのにちょうどいい大きさです。2杯目、3杯目を2人で分け合ってもいいし、同じデザイナーさんの小さな湯呑みなら60mlを3人分に分けて振る舞えます。
大きすぎず、小さすぎず、程よくミニマムな大きさが私の用途にぴったりでした。また、見た目はシンプルで美しく、手触りも良いです。お気に入りの急須です。
華やかさと爽やかさを兼ね備えた甘みのあるお茶。これだけで満足感があり、気分転換したい時などにチョイスしています。
お茶請けを用意するなら洋菓子にも合わせやすく、紅茶やコーヒーはちょっと重い…という時にも。
特に柑橘系など、香りの良いお菓子と合わせるとお互いが引き立つのでおすすめです
お店で頂いた香駿の冷茶が素晴らしく美味しく、茶葉によってこれほどまでに違うのかと、私の中での新たな扉が開いたお茶でした。
あの香りが忘れられないのですが、茶葉の量か、水なのか、自分で淹れるとなかなかあの美味しさにたどり着けずにいます。
通年販売のお茶ということもあり、ほぼ1年を通して楽しんでいます。
お茶だけでも美味しいですが、甘味とも塩味どんなお茶請けとも相性が良いです。
餡子系などの和菓子の美味しさを引き立て、バター系などの洋菓子にも負けない存在感。
にこまる玄米とも相性が良いのでおすすめです。
人を選ばないバランスの良さがあり、それでいて誰に出しても「美味しい!どこのお茶?」ときかれる確かさから、誰かに緑茶をおすすめしたり、贈る際にはこの茶葉からというひと品です。
コロンぽてっと、触り心地が良くて、丁度良いサイズの塩壺でした。少し黄味かかったベージュのお色にホッコリ癒されます。可愛さ満点のお品ですが、シンプルなデザインの為、どんなキッチンにも馴染んでくれるのではないでしょうか。私は出しっぱなしにして、ずーっと使い続けていきたいです。
こういったサブスクリプションの良い点は、お茶の選択に自分の意思が介在しないところだと思います。自分で茶葉を選ぶと同じような傾向になってしまいがちですが、普段自分では選ばないであろうお茶に自動的に出会えるのは、幅広く経験したい人には最適です。量と価格もちょうど良いです。
毎月届くお茶は、普段慌しく生活している私に、癒しの時間を与えてくれます。様々な香りや味に出会えるこのシステムも気に入っています。もし、聞いていただけるなら、煎茶のみのコースも作っていただけると有り難いです。煎茶の奥深さに気づけたのがこのサイトからだったので、今のコースに合わせて、煎茶のみのコースを作っていただけることをのぞみます。
お茶の風味とペアリングで季節を感じられ、冊子を読みながらほっとひと息つけるのが癒しになっています。TOKYO TEA JOURNALのおかげでこういう時間を自然と作れるようになりました。
昔、ここのお茶を頼んでて、辞めちゃったんですけど、やっぱり、また、ここのお茶が、恋しくなり、頼みたくなるくらい、美味しいんですよね。色々なお茶が、飲めるのが、いいんですよ。
記載されているように液だれはなく、気にせず安心して飲み物を頂けます。また通常の持ち手と比べ角張っているからか滑りずらく持ちやすいです。
濱岡さんの作品はどれも使いやすく、長く愛用できる品々ばかりです。
ちゃんとした茶器を使った事はなかったのですが、見よう見まねで冷茶を入れたピッチャーと茶杯を用意して毎日いただいてます。
茶杯は5、6口程の量なんですが、茶杯には氷を入れず、常にピッチャーで程よく冷えたものをいただけるので、じっくりとお茶を味を楽しめ、また素敵な雰囲気も味わえて、とても満足しています。
高橋さんのグラスは、円やかという表現が正しいのでしょうか、薄すぎも厚すぎもない絶妙な厚さと相まって、ガラスなのに持った感じや、口の当たるところに角というか硬さを感じない不思議な趣きがあるんですよね。とても気に入っています。
大きさも使いやすく、可愛くてなんと言っても素材感が好きです。焼き物などは写真と届いたときで印象が違う事もありますが、イメージ通りでした。形もカワイイので色々活躍しそうです・
白桃烏龍茶 翠玉を何度もリピート買いしています、すっきりした味わいで夏に適したお茶ですが、秋になっても美味しいものは美味しいのでしょう。秋の味わいも確かめようと思っています。
購入する際、どれにするか迷わなくていいので
とても嬉しいです
最近忙しくお茶を楽しむ時間が取れませんが
又、購入したく思います。
一度 美味しいお茶見つけ検索しましたら完売となっていました。
気づいた時には売り切れで買えなかったので再販を楽しみにしていました。
一緒に販売されている茶そばやお茶のそうめんの薬味に使いました。
海苔が手で千切ったような大きめのサイズで、風味豊かに感じます。
パッケージに使用例がイラストで記載されている所も良いなと思いました。
美味しかったので友人にお裾分けしたところ、とても喜んでいただけました。
炭酸でお茶を淹れるなんて頭に無かった。本当、目からウロコでした!さっそくオススメの淹れ方で飲んでみると新発見!!今まで生きてきた中でやってみたことがなかったので新鮮過ぎて、生きる楽しみが増えました!

 ログイン
ログイン カート
カート