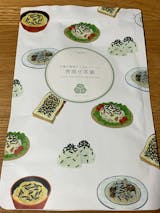桜染めのことを教えてください。Maito Design Works 小室真以人さんに聞いた、桜染めの色の種類と手順
2021年03月11日
春の訪れを知らせる、淡い桜色。この桜色は、花びらではなく枝や、樹皮から色を取り出すことで、布を染め上げることができます。美しい桜の花を色づかせる力は、幹や枝、桜の木全体に秘められているのです。
この桜色を取り出すためには、伝統的な草木染めの技法だけではなく、化学的な理論の組み立てや実験という現代的な手法が不可欠でした。毎年違う表情を見せる自然を相手に、その恵みの魅力を引き出す歩みには、お茶づくりと共通した想いが感じられるような気がするのです。
今回は、そんな「桜染め」の色の種類や、手順についてご紹介します。
教えてくれたのは…小室真以人(こむろ・まいと)さん

1983年生まれ。家業の草木染め工房(工房夢細工)で草木染めに触れる。東京藝術大学美術学部工芸科で染織を専攻し、伝統技法を学ぶ傍ら、革の草木染めなどの新しい技術表現を模索。2008年 自身のニットブランド「MAITO」をスタート。2010年にマイトデザインワークスを設立し、東京都台東区上野の2k540に直営店を出店。2012年に台東区蔵前にアトリエショップをオープン。毎月開催されるワークショップも人気。
公式サイト:https://maitokomuro.com/
桜の木から何色に染まる?

桜の木に含まれる色素はピンクだけではありません。黄色やベージュ、灰、さまざまな色が含まれています。草木で布を染めるには、金属質(銀イオン)の成分で色を定着させる「媒染」をする必要があります。染めの色は媒染に使う金属の性質や、使う桜の部位で変わります。

桜色
小枝や蕾など、花に近い部位が、布を桜色に染めます。アルミ性質(※)の媒染で定着させます。
※アルミ性質の媒染には、ミョウバンや木(楮)の灰などがある。

花葉色(はなばいろ)
樹皮を使うと、ベージュに近いオレンジ色に染めあがります。アルミ媒染で定着させます。

淡黄色(たんおういろ)
樹皮の内側にある芯材や初夏の葉を使うと、黄色を帯びた色味に。アルミ媒染を使います。

灰鼠色(はいねずいろ)
桜の木から、薄いグレーを取り出すことも。触媒には鉄を含むものを使用します。
桜染めの手順
【1】枝を細かく刻む

花の咲く前の小枝を手に入れたら、その日のうちに細かく刻み、色素を抽出します。枝の中が黄緑色の状態の生木がベスト。ソメイヨシノでピンク色を、オレンジがかった色味は八重桜や枝垂桜で染めます。
【2】抽出を繰り返す

小枝や樹皮などを細かくしたチップと水、少量の米酢を加えて火にかけて沸騰させます。120分ほどしたら布で濾しさらに3〜4回程煎液を抽出。抽出した煎液を1週間ほど寝かすと、酸化されて赤みが増します。
【3】布に染み込ませる

色素は水溶性のため、布に定着させるためには媒染が必要です。黄色から桜色に染める場合はアルミ、茶色なら銅、灰色なら鉄を含む媒染を行ってから、沸騰した煎液に布を入れ、煎液をしみ込ませます。
【4】乾燥させて、完成

一度に濃く染めようとすると、別の色が混ざってしまうため、短時間の染色を何度も繰り返します。染めあがった布は、しっかりと天日に干して乾燥させます。乾くと布に花の色が移ったような桜染めに。
美しく優しい色合いの「桜染め」。今年は、街に咲く桜の花だけでなく“枝”にも注目して見てみてください。今まで気がつかなかった、枝もほんのりピンクの色だということに気がつきます。
樹皮から色を取り出す瞬間、「命の色をいただいている」気持ちになると教えてくれたのは、Maito Design Worksの小室真以人さん。インタビューも合わせてご覧ください。
草木染めのプロダクトを見る&買う
Maito Design Works 蔵前本店
東京都台東区蔵前にある、ブランド「MAITO」のアトリエショップでは、「MAITO」のほぼすべてのアイテムが取り揃えられています。また、草木染めの染色工房とショップが隣接しているので日によっては製作現場を覗くことも…?毎月、草木染めの体験ができる草木染めワークショップも開催中。
東京都台東区蔵前にある、ブランド「MAITO」のアトリエショップでは、「MAITO」のほぼすべてのアイテムが取り揃えられています。また、草木染めの染色工房とショップが隣接しているので日によっては製作現場を覗くことも…?毎月、草木染めの体験ができる草木染めワークショップも開催中。
| 所在地 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-14-12 1F |
| 電話番号 |
都営大江戸線 蔵前駅:A6出口より徒歩9分
JR総武本線 浅草橋駅:浅草橋駅東口より徒歩11分
その他の店舗はこちらから
このインタビューは「TOKYO TEA JOURNAL」VOL.23に収録されています。
TOKYO TEA JOURNALとは?
他の記事もみる
購入する際、どれにするか迷わなくていいので
とても嬉しいです
最近忙しくお茶を楽しむ時間が取れませんが
又、購入したく思います。
一度 美味しいお茶見つけ検索しましたら完売となっていました。
気づいた時には売り切れで買えなかったので再販を楽しみにしていました。
一緒に販売されている茶そばやお茶のそうめんの薬味に使いました。
海苔が手で千切ったような大きめのサイズで、風味豊かに感じます。
パッケージに使用例がイラストで記載されている所も良いなと思いました。
美味しかったので友人にお裾分けしたところ、とても喜んでいただけました。
炭酸でお茶を淹れるなんて頭に無かった。本当、目からウロコでした!さっそくオススメの淹れ方で飲んでみると新発見!!今まで生きてきた中でやってみたことがなかったので新鮮過ぎて、生きる楽しみが増えました!
抹茶ラテと抹茶ケーキを作りたくて購入いたしました。粒子が細かく溶けやすいので、ドリンクでもスイーツでもダマにならず作りやすかったです。お味も香りもしっかりと感じられ、美味しさが鼻を抜けていくようでした。
ジャスミンはとても美味しいです。透明の割れない急須で飲んでいるのですが、茶葉の広がりも楽しめて薫りもホッとするもので、お昼休憩に愛用しています。
日頃から透明急須を愛用しているので友人のバースデープレゼントとして贈ったところ、大変喜んでくれました。お茶はお任せにしたところ藤井風のファンの友人にピッタリなきらりと言う名前のお茶だったのも良かったです。
半信半疑で購入したところ、予想以上に美味しくて!再購入と思ったら完売で!がっかりしました。
次回の販売に期待しています。
プレゼントにも良い感じのパッケージなので、待ち遠しいです!
旅行用に購入しました。
旅先ではペットボトルやティーパックが多いので、温かくておいしくいれたお茶を飲みたいと思い、購入しました。割れる心配がないというのが何より安心です!茶葉がゆっくり開く様子をのんびりと眺められるのは贅沢な時間です^_^
デザートにもサラダにも、ちょっとしたおかずにもちょうど良い大きさで、毎日使っています。
とても素敵な花瓶でした。今はハーブを飾っています。お部屋にとても馴染んで自然な雰囲気がとても良い感じです。
毎回楽しみに届くのを待ってます
茶葉に合わせてプチ贅沢して
お美味しい和菓子や洋菓子と頂いております
特別感を味わいながら
明日への活力となっております
いつも各地のシングルオリジンのお茶を楽しめるのがありがたいです
自分で選ぶと特定の物に偏りがちなので様々な種類のお茶を試せるのは素晴らしいと思います

 ログイン
ログイン カート
カート